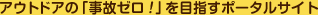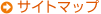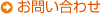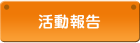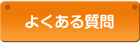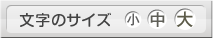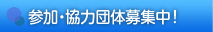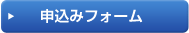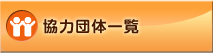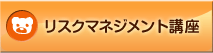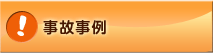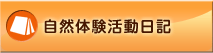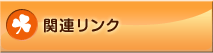浮いて待てとは言うけれど・・・
猛暑のニュースと水辺の事故のニュースが毎日入ってきますが、一言で「水辺」といっても様々な環境があります。
海、川、ため池、湖etc…
最近見かけたニュースでは、「基本的に溺れている人を助けに行かない‥‥心情的には…どうしても我が子のそばに行きたくて行った、そのときに、親子で一緒に浮いて救助を待っていて欲しい…。という記事がありました。
文脈を見れば、「一般の人は助けに行かない」という記事なのですが、「一緒に浮いてまて」って伝わってしまうと、単純に要救助者が1名から2名に増えてしまうことになります。
要救助者を発見したら、「周囲の人に知らせる」「119番通報する(海は118番)」「浮くものを投げてやる」「見失わないように声をかけながら観察する」「自ら水に入って救助しようとする」のは絶対にダメです。「浮いて待つ」状態にならないようにすることが一番大切です。
「もしも自分の子どもが!」と思うなら、事前にライフジャケット準備し、子どもも保護者も着用して水辺に近づきましょう。もしもの対策をしてから水辺に近づいてください。
Xに次のような投稿がありました
6月19日,20日、海上保安庁の協力のもと、日本ライフセービング協会と合同で、「溺水事故防止に資する実証実験」を実施しました。海では浮いて待てないリスクが大きいことが実証されました! pic.twitter.com/aZzCxIGtYu
— 公益社団法人日本水難救済会【公式】 (@Qsuke_MRJ) June 21, 2023
特にも川には流れがあるので、たとえ上手に浮いてられたとしても、流されてしまえば浮いて待てでは間に合いません。
大切な命を守るためには、準備が大切です。
以下、関連記事
子ども水辺サポートセンター
子ども水辺サポートセンター
全国の水難事故マップ(川・湖沼地等)は、河川財団が川などの水辺へ出かける人向けに、過去にどこでどのような事故が起きているかを伝えるためにまとめたものです。川で体験活動や川遊びをする際にお役立てください。
※川の活動では、事前の知識得た上で、ライフジャケットを着用し、気象や水位などのリアルタイム情報を活用してリスクを回避しましょう。